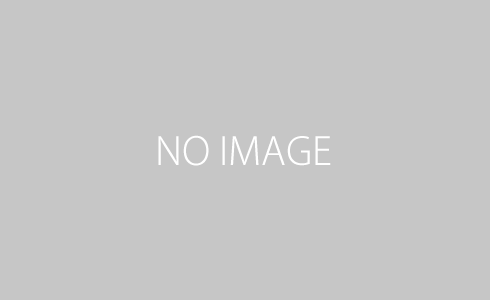「大切なゴールデンエイジを無駄にしないこと!」
「好きこそ物の上手なれ!とにかく楽しく自由に!」
◆ボールタッチ回数が多い
→技術力向上につながる
◆プレー回数が増える
→判断回数増加につながる
◆11人制よりも観るものが減る
→判断の明確化につながる(判断要素が簡略化されているということ)
◆どのポジションでも攻守に関わり続けられる
→サッカーの全体像を理解、関わることの習慣づけにつながる
◆ゴール前の攻防が増える
→得点力・守備力向上につながる
要するに8人制サッカーは、
▶︎子どもたちでも理解しながらプレーできるように簡略化されたゲームである
▶︎その分、1つ1つのプレーがゴール、および勝敗を大きく左右する
▶︎したがって、個々の未熟な所が露呈しやすいが、本人にもそれは実感しやすい
▶︎だからこそ、子どもたちが本物の技術と判断を磨くには最適なトレーニングであると捉えることができると思われます。まさにサッカー導入期の小学生にはウッテツケなゲームです。じゃあ、「本物の技術ってなに?」…技術(≒スキル)には判断を伴うオープンスキルと、判断を伴わないクローズドスキルがありますが、
サッカーで求められる本物の技術はオープンスキル、すなわち判断を伴う技術だと言えます。じゃあ、「本物の判断ってなに?」
サッカーに「こうすればうまくいく」という絶対的な正解はありません。
その中で選手たちは迅速かつ的確な判断を常に求められています。判断は選手自身のものです。
だから、「今の判断はあーだったこーだった」と外野が口にするのは自由ですが、選手が聞き入れる必要は特にありません。
ただし、サッカーには「こういう時には基本的にこうすべきだ」という「原則」があります。
相手との駆け引きの中では敢えて「原則」とは逆のプレーが上手くいく場合も往々にしてありますが、本来は"逆のプレー"も「原則」を認識できているからこそのモノです。
したがって、「原則」抜きの判断ミスには言及の余地がありますから、選手はコーチや仲間からの声に耳を傾け、そのミスから「原則」を学ぶべきと言えるでしょう。
よって本物の判断とは、「原則」に基づくものと言えます。
…であるならば、あらゆるプレーの大元には「原則」があるということになり、それがとても重要であることがわかります。
ただし、原則にもいろいろあります。
例えばチームの約束事レベルの原則は、
監督の志向性などによってコロコロ変化するモノなので、
サッカー導入期の小学生が学ぶモノとして優先される必要はありません。
対して、例えば"攻撃の優先順位”のような、サッカーの本質上揺るぎない原則は、サッカー導入期の小学生こそ学ぶべきであり、
そのために8人制(簡略化されたゲーム)が採用されていると言っても過言ではないはずです。
したがって、8人制サッカーでは、
簡略化されたゲームであるという特性を最大限に生かすことが重要です。
すなわち、たくさんボールに触れ、ゴールや勝敗を左右するシーンに数多く関わり、たくさんミスをして、そこから原則を学び(身体で覚えていき)つつ、本物の技術や判断を磨いていくということ。
もちろん、サッカー大好き!という心を守り育むことも大切、ボールマスタリーも大切、発育発達への配慮も大切な中で、
8人制サッカーでは「原則を学ぶ(身体で覚える)こと」もまた大切なのではないかと思います。
※本当の判断ってなに?…のクダリは、『フットボール批評 3月号』に掲載されていた、岩政大樹さんのコラムを参考にしながら、僕の意見をまとめました。興味のある方は、『フットボール批評 3月号』をぜひご覧ください。
※なお、当クラブは『フットボール批評』を萩市立図書館「萩あいぶらり」に毎月寄贈しています。ぜひとも活用して頂ければ幸いです。