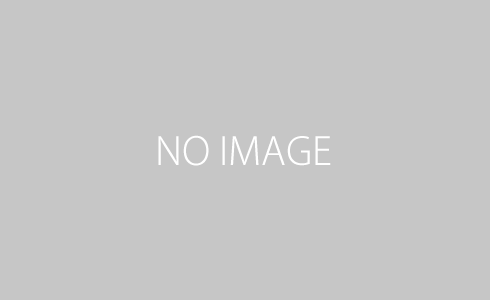まちづくり=ひとづくりという環境に長く身を置いていると、いくつかのパラドクスにぶち当たる。
あるある話でいえば
①「早熟は大成しない」
でも、ある程度、成功体験がないと続ける気にならない、上を目指そうと思い難いのも確か…。勉強でもスポーツでも優秀であるなら能動たる貪欲さを必要とするが、育成年代に挫折少なくいると貪欲さを育むことが難しい。
※なるほど!M上は将来の職業が決定付けられているから成功体験があっても貪欲なのかもしれない。
②「資質の高い子を育てると親は将来淋しい思いをしがち」
資質の高い子は活躍の場を求めていくので地元に残ることは少ない。例え話(実際にあった話)だが、二つ並びの家庭があって、どちらも同じ世代の子どもがいて、片やとても学業優秀の優等生、片や勉強ができないどころが問題ばかり起こす劣等生。育成年代のときは優等生の子を持つ親は鼻高く自慢の子ども、劣等生をもつ親は迷惑かけたところに頭を下げることが多く、自慢できるどころの話じゃない。劣等生の親はお隣がとても羨ましかったとのこと。
しかしながら、大人になり、優等生は地元を離れ都会で暮らし、家族を持ち、実家に帰ってくるのは数年に1度。対して劣等生は、地元でガテン系の職につき、結婚し子宝に恵まれ、両親と同居し、大家族で毎日賑やかに暮らしている。
年老いて優等生の子を持った親は、賑やかなお隣がとても羨ましかったとのこと。
あと、優等生であればあるほど大人になったとき自分が積み上げてきたものに自負があるから、とてもめんどくさい。(笑)
どちらが良いのかなんてわかったもんじゃない。
※まぁ色々なライフスタイルが認められたし、ネットも普及したので例え話は時代錯誤かもしれない。
それでも、優秀であるというのは必ず何かと引き換えるものがあるし、劣等ばかりであれば発展は難しかったりする。
2元論で考えるべきことではないテーマ。
ということを、節目の時期、挨拶にくる元教え子との会話の中で改めて感じる。
「出会いの春。別れの春。」
子育てに正解があるとすれば「愛」と「感謝」しかないのではないかと思う。結果ではない。